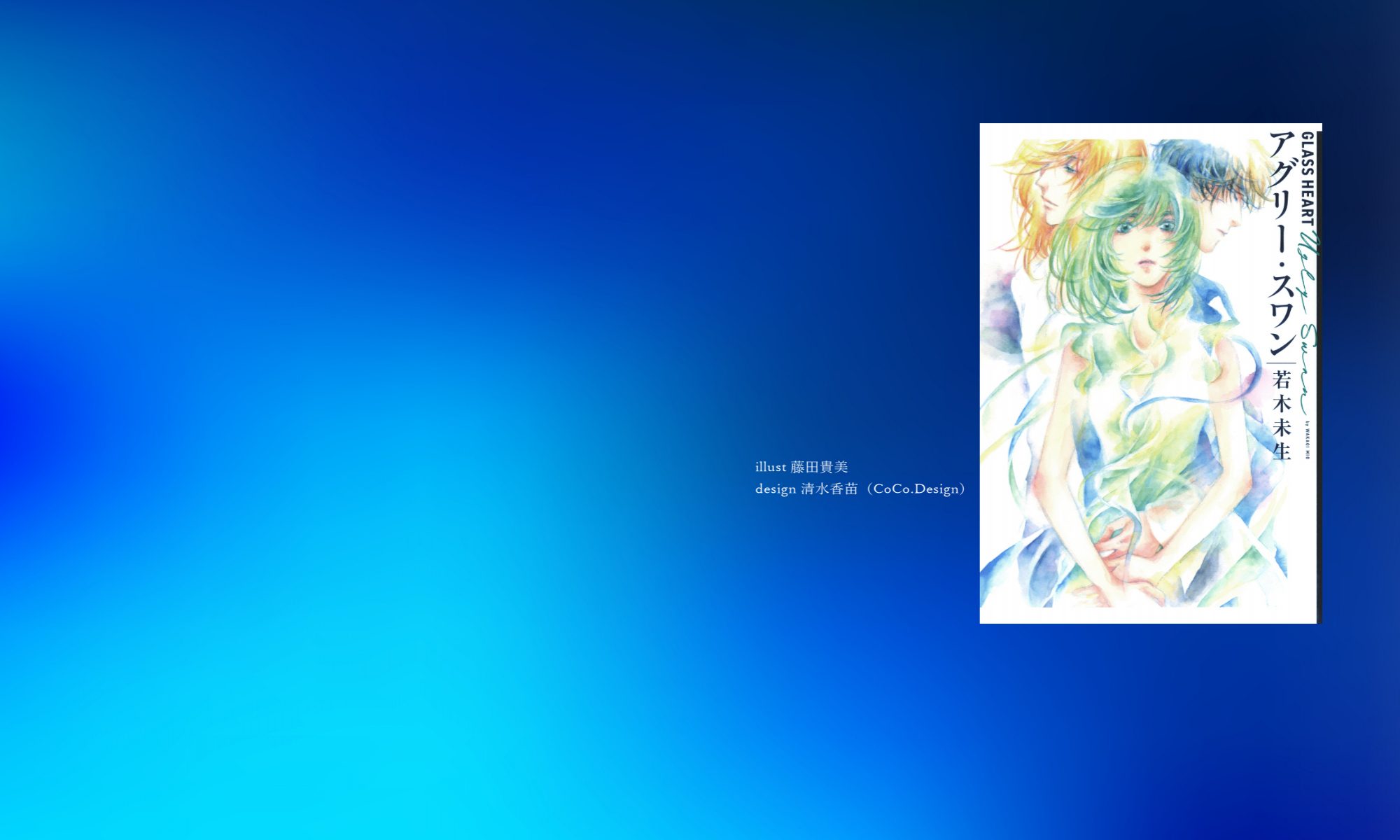M 先生自身がいちばん好きなオーラバのキャラは誰ですか。それとも、やっぱり一番は決められないでしょうか。
若木 けっこう聞かれるんですよね、この質問は。でも毎回ね、その時によって好きな人が違うんですよ。こないだまでは「亮介」くんが一番好きだったんですけど、その前は「忍」さんが一番好きで。今は誰だろう……。今は……、『不滅の王』という話を書いたばかりなので、「炎将」が一番好きかな(笑)。そういう風に順繰りにめぐっていくわけです。で、コイツは嫌いだっていう人はいないんですけど、でも100%許して完全に好き、嫌いなところはないっていう人も、それはそれで居ないかな。ちょっとずつ好きだし、でもここはどうよってところもあるし。でも、みんな好きですよ。
A 「文学メルマ!」に書かれた『ラッシュ』を先に読ませていただいたんですが、あそこに登場するギタリストの高岡さんは『グラスハート』の高岡さんですよね?
若木 そうですね。同じ人ですね。
A 『ラッシュ』は、『グラスハート』とくらべて時間的にどのあたりなんですか。
若木 グラスハートの彼は、今26歳になったばかりなんですけど、『ラッシュ』のほうだと、すでに27歳で。その辺でなんかあったのかな、と(笑)。
M これからグラスハートを読んでいくと何かあるのですか?
若木 どちらにもとれるように、とは思ってるんです。別々の次元の人だなあと思って読んでもいいし、でも繋がってもいる。そもそもデビュー作の前に、受賞作、コバルトノベル大賞で佳作をもらった作品があるんです。『AGE』っていう、高校生たちが主役のストレートな青春小説で、そこにも「高岡」くんがいます。グラスハートではもっと音楽が大きな要素になっていて、『AGE』とは別の主人公のための別の物語ですね。ただ、その二作品にまたがる高岡くんの人生は、一貫して継続されるものでもある。『AGE』って話があって、『グラスハート』って話がある。それぞれに「高岡」くんって人がいて、別々の話にも読めるけど、繋がってもいるという。その構造と、『ラッシュ』も同じ感じです。
M 先生は「文学メルマ!」で初めてライトノベルの枠を越えたと思うんですが、それにあたって、小説の書き方や若木先生御自身の意識に変化はありましたか。
若木 いえ、正確には、初めてではないんです。すこしずつ、ジャンルや年齢層の境界をこえるお仕事は始めているので……。
ただ、そうですね、ライトノベル、つまりティーンエイジャーの人が手に取りやすいパッケージの本であったり、お小遣いで買える値段の本っていう、このジャンルには、私自身がすごく愛着もあるし、自分なりの誇りも感じているんです。だから一口に「ライトノベル卒業」と言っちゃうような状況には、自分を置いてないですね。
そのあたりは、はたから見て、「どっちの住人なの?」って思われる要因という気もします。すっきりカテゴリーで分類するのがむずかしいような……。
そもそも、小説を書いているときに、ライトノベルを書こうとしていても、これはライトノベルなのだぞ、って思って書いてるにしては、私の作品ってどうもなにか枠をはみだしちゃうんですよ。ライトノベルはすごく好きで、面白いものを書きたいとか、エンターテイメントだぞ、コバルト文庫だぞ、中学生、高校生の人達が読むんだぞ、っていう意識はあるんですけど、でもどっか必ずはみだしてしまう。
はみだしちゃうのが私の特徴というか、クセなのだなあ、と思っていて。それは、自分の悪癖だと思って、一種のコンプレックスでもあったんです。まあ、でも、コンプレックスって自分で悪く思うよりは、プラスの方向にうまく役立てたほうがいいだろうと、今は考えてます。
「文学メルマ!」にお誘いいただいたとき、私にどんな小説を求められているのでしょうかってきいてみたんです。なるべくライトノベルらしさが残っている方がいいのか、はみだしちゃった部分がいいのか。でも、「若木さんの作品である、というガンとしたものであればいいです」みたいなお返事を……うーん、うまく言えないけど、「若木さんの作品をくれ」という言われ方をしたように思うんですが……、どうでしょう?(笑)
編集部 そうでしたね。
若木 つまり、枠をどうこう考える以前に、もっと大きいことを要求された気がしまして……(笑)。
編集部 「文学メルマ!」自体の読者層もはっきりしていないんですよ。十代から五、六十代までという幅広い。
編集長 ぼくは小説をカテゴライズするのが好きじゃないんですよ。小説は小説だから。若木さんらしいものをとしかお願いしてないんですよ。
若木 あえて考慮することがあるとしたら、ジャンル分けよりも、メディアがインターネットであるということですね。誰でも読めるという。
今、「文学メルマ!」で並んでいるお名前の中に、いきなり「コバルト文庫の若木さん」をいれてくださったというのは、枠組み、垣根が非常にとっぱらわれている感じがして、それは私自身もびっくりしました。わあ、自由な場所なのだなあ、と。
(続く)
※初出 2002年「文学メルマ!」